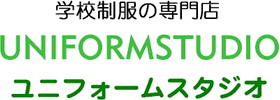海洋プラスチック汚染問題にふれて
のんびりと過ごした夏休みのある1日、とある学習会に参加してきました。近ごろは新聞社などが主催する無料ないしは有料の講演会、学習会が結構あって、ネットを通じて条件さえクリアすれば誰もが申し込めるようになっています。学生時代は「もうちょっとがんばって勉強すべきだった」と反省しきりですが、その時期から遠く離れた頃に何となく学びたいなと思ったりするから不思議なものです。
といっても、興味がなかったり、難し過ぎて複雑怪奇なテーマであったりすると足は遠のきますが、今回のテーマは「海洋プラスチック汚染」問題。プラスチックごみの現状と今後を扱った内容で、誰もが考えるべき事例であり、なおかつ強く興味があったのは、これまで何度か足を運んでいる沖縄・西表島での惨状を目の当たりにしてきたからです。
夏もそうですが、とくに冬になると西表島の浜にはさまざまなごみが漂着します。浜を覆うほどの量の多さで、ここの場合は日本のメーカーのペットボトルよりも韓国、中国など近海からのものがめちゃめちゃ多く、その様子にびっくり。いったいどういう捨て方をしているのか!と、思わず叫んでしまいたくなるほどです。
日本が、諸外国がどうこうは別として、日常生活から川などを経て海に至るプラスチックごみは、世界の海に漂流、またはこうして海岸に漂着します。そして、漂着と漂流を繰り返すうちに劣化して細かく細かく砕かれて、やがてマイクロプラスチックといわれる微細片となります。これが結果的にどんな影響をおよぼすのかは、すでに多くの人が知るところです。
微生物の体内に侵入し、それを次に大きな魚が口にし、さらにより大きな魚がその魚を体内に入れ、こうした誤食が繰り返されたあげく、私たち人間もこうした魚を食べることで体に悪影響を及ぼす危険が増します。海洋生態系への影響はとてつもなく大きいうえ、それがこれから生まれ育っていく子どもたちにも連鎖していくと思うとぞっとします。
学習会では日本各地の浜の惨状が紹介され、プラスチックごみは日本全国で10万トン規模とのこと。と、数字を言われてもピンとこないのですが、各地で清掃活動が行われてもまったく追いつかず、人の力ではもはや限界。世界の海洋ごみトップ3は、レジ袋が16%、テイクアウトの食品容器が15%、ペットボトルが13%で、ほかに発砲スチロールなども多く漂着しています。どれも私たちの生活の身近にあるもので、海に流れ出れば海流と共に世界中の海を回るわけですから恐ろしい話です。
う~む、この問題を解決するためのもっとも有効な答えはあるのでしょうか・・・。細かく砕かれたマイクロプラスチックになる前に回収することはもちろん、とにかく私たちがごみをきちんと捨てて処理することが何より大事でしょう。各自治体でプラスチックリサイクルはされていても、袋に別のモノが混入したり、汚れの多くついたものがあったりと、正しくリサイクルできるのはほんのわずかだという話も聞きました。これでは本末転倒です。
この学習会のあとはしばらく、ペットボトルの飲料を買う気にはなれませんでした。それはマイボトルで代用することがいくらでもできますが、スーパーでは容器に入った食品を当たり前に買ってしまうし、パンもトレーからトングでそのまま取る店もあれば、1つずつきちんとビニール袋に入れている店も少なくなく、ゴミを減らすのは容易なことではないことは明白です。
解決方法についての主体的学びを、各学校でもしているのではないでしょうか。私たちにできること。それはこの問題だけではなく、生活に関わるいろいろなことがあるでしょう。せっかくの学習会参加、頭の回転が大きく鈍る自分に気づく一方で、自分なりにやれることはやっていきたいし、その思いを少しでも長く持続させなくちゃと思います。あっという間に忘れて元の自分に戻ることがないようにしなくちゃいけませんね!